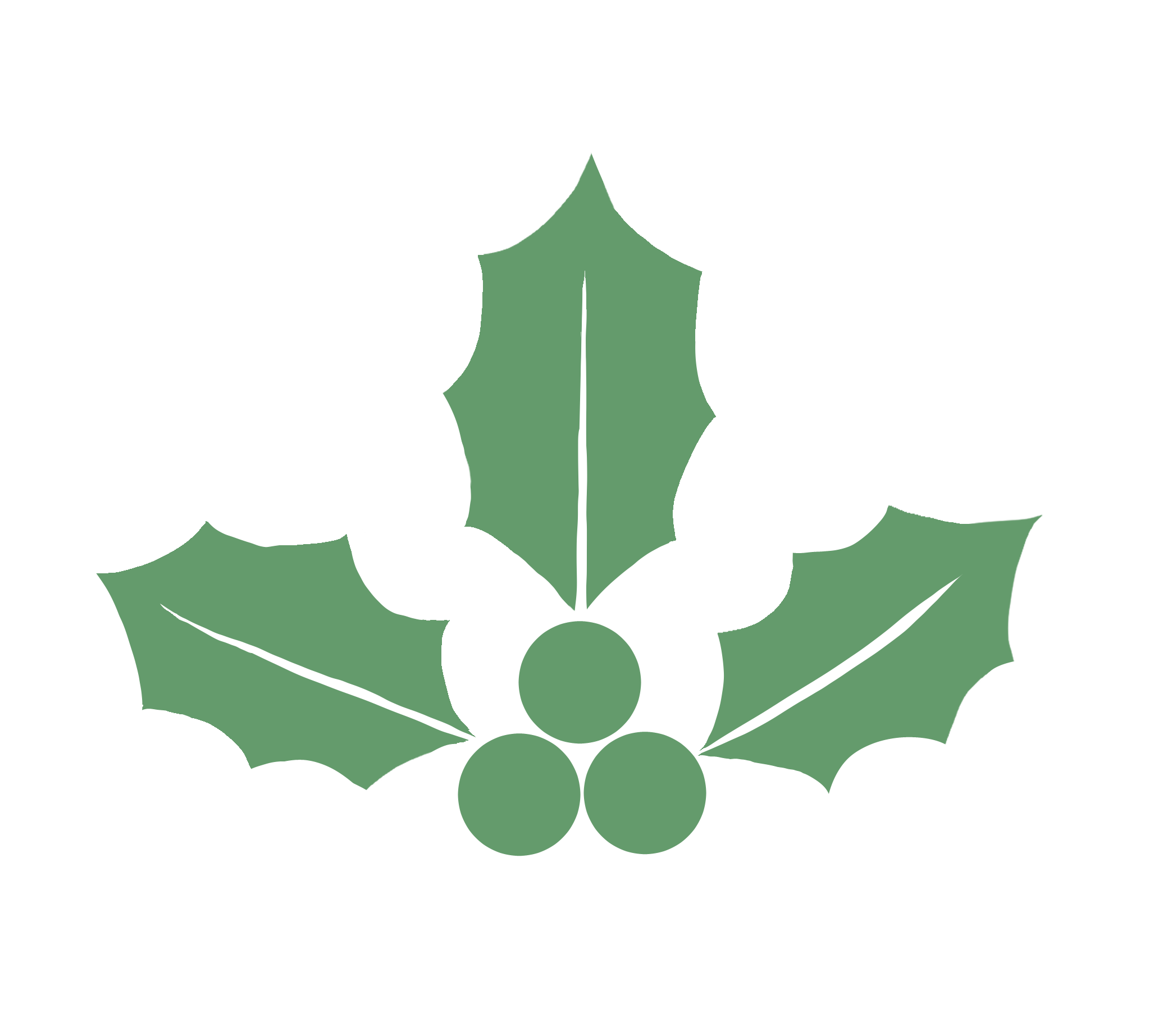わが国は、古来より多種多様な災害に見舞われてきました。
わが国の面積は37.8万㎢で、地球の陸地面積の0.25%です。この狭い国土に、世界の火山の7.4%、世界で上陸する台風の9.7%、世界で起こるマグニチュード6(M6)以上の地震の15%が集中しています。これらの国土の地理的な条件に加え、都市部に人口が集中し、工業地帯が立地していることなどの社会的な条件を踏まえると、わが国は世界で最も災害の起こりやすい国、つまり災害大国といえます。
わが国にとって災害とは、起きるか否かではなく、いつ起きるかが問題なのであり、そのために普段から災害への備え、つまり防災対策を行うことがとても重要となってきます。
防災対策の基本として、「自助」「共助」「公助」が重視されています。個人が自ら災害に備える「自助」、隣近所で助け合う「共助」、国や市区町村などが行う「公助」、この三者が相互に連携し、適切に組み合わせることで、もし災害が発生した場合に、迅速に人命の保護、被災者の救援を行い、復旧・復興に取り組むことが求められます。
しかし、近年の少子高齢化により、「自助」「共助」「公助」のどれもが脆弱になりつつあります。「自助」の分野では、災害時要支援者が確実に増えています。2035年には75歳以上の高齢者が全人口の約20%に達すると見積もられています。「共助」も、共助の主体である自治会の加入率や消防団員の数が減少しています。「公助」についても、災害対応の主体となる市町村役場の職員数や土木技術者の減少が続いています。
災害は確実にやってきますが、「自助」「共助」「公助」といった防災対策の基本が年々弱まっているのがわが国の現状なのです。しかし、このまま放置するわけにはいきません。
もちろん、国を挙げてハード、ソフトの両面で防災力の強化の努力は続けられていますが、これからは、今まで以上に、企業が地域社会の一員として主体的に地域防災に関わる努力が求められる時代となります。実際に、災害が起きたとき、被災者に自社製品を提供したり、地域の復興作業に自社の従業員をボランティアとして参加させる企業が増えています。
一般社団法人日本防災訓練士協会は、企業の持つ人材と組織力を防災の視点で見直し、企業の従業員の力を、「共助」の一翼として役立ててほしいと願っています。
企業が災害時に主体的に行動するには、それを牽引できる人材、つまり「防災訓練士」が必要です。
防災訓練士とは、災害全般に関する知識があり、BCPをマネジメントする実務能力を持ち、災害時に企業防災の主役としてリーダーシップを発揮し、共助の分野でも貢献しようとする熱意を持つ人材です。