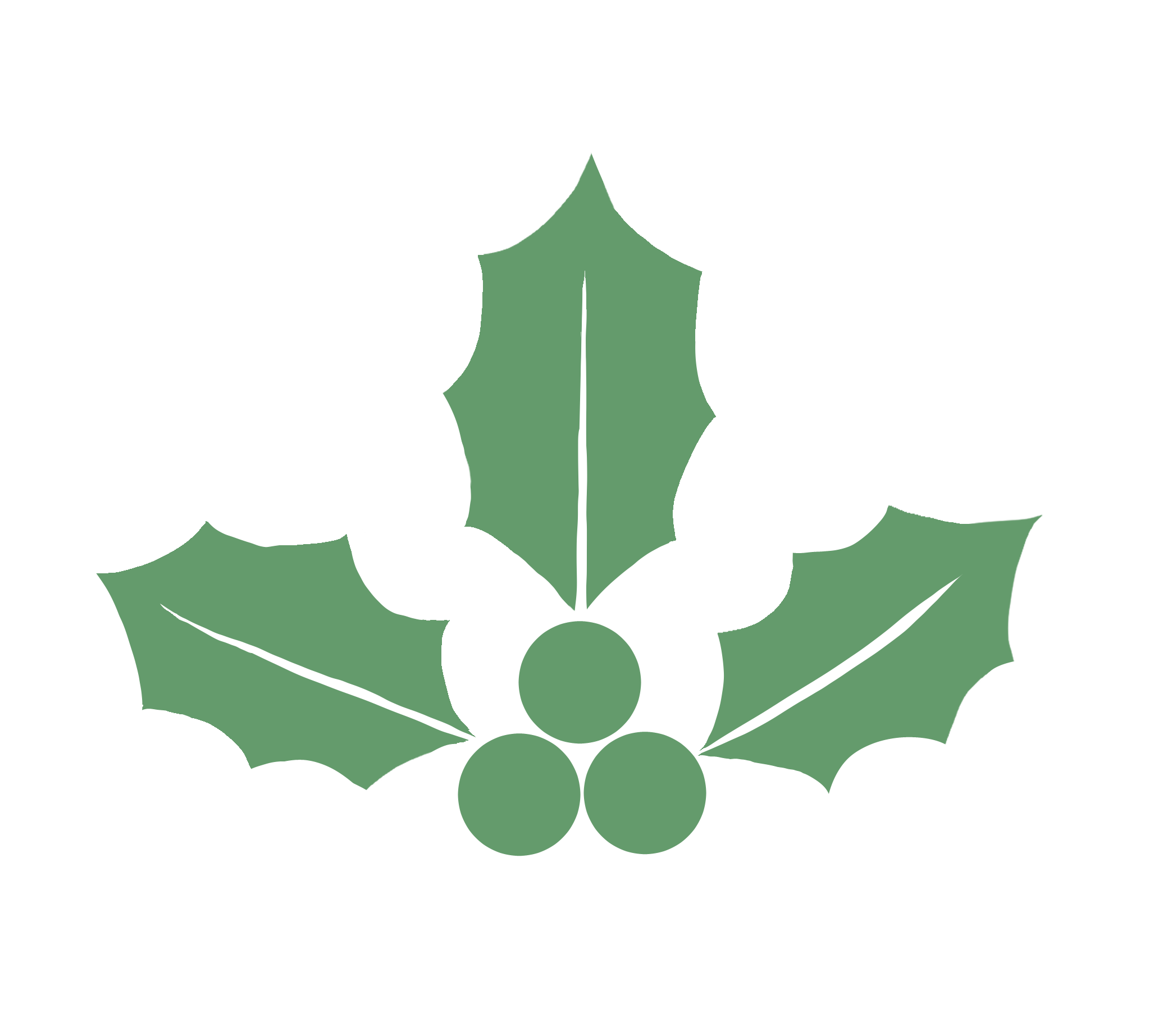しばらく中断していましたヒイラギ通信を再開することといたしました。この通信のシンボルであるヒイラギ(柊、学名: Osmanthus heterophyllus)は、モクセイ科モクセイ属に分類される常緑小高木の1種で、冬に白い小花が集まって咲き、甘い芳香を放つ。とげ状の鋸歯をもつ葉が特徴で、日本では邪気を払う縁起木として生け垣や庭木に良く植えられる。また、セイヨウヒイラギは冬になると赤い実が美しく、クリスマスの装飾の定番としても使われています。日本での柊の花言葉は「先見の明」「用心深さ」など。また欧米で一般的なセイヨウヒイラギは、「防衛・防御」「家庭の幸せ」などとされています。
このように柊の花言葉には、無闇に結果を求めず物事を慎重に進めリスクを回避する賢さと、不運や悪い結果から家族や友人など大切な人を守れる強さを願うものと考えられます。新しい年を迎え新たな気持ちで、柊にあやかって「災害に強い企業・街づくり」に、皆さんと一緒に歩み続けたいと願っています。
昨年は、関東大震災から100年目の節目の年でした。1923年に発生した日本の近代史上最も被害を出した地震は、死者・行方不明者は10万5,000名以上、焼失・全損家屋30万戸に上り、電気・水道・道路・鉄道などのライフラインにも甚大な被害が発生、首都・東京や横浜も壊滅的な被害を受け、想像を絶する大災害となりました。
このような巨大地震の経験から、これまで大地震に備え様々な対策を講じてきました。新たに建築基準法を制定して建物を不燃化・耐震化、道路拡幅や緑地の確保、木造密集地域の解消など、防災的な都市計画を推し進めるとともに地域の特性に応じた防災計画を策定し訓練も実施してきました。この100年間、当時の被害と学ぶべき教訓が数多く伝えられ、その都度しかるべき対策をとってきたましたが、その教訓を超える事態が発生し、また学ぶという営みを繰り返しています。
「もはや地球温暖化ではない。地球沸騰化の時代に入った」と、国連が警鐘を鳴らした昨年年7月、世界の平均気温は観測史上最高を記録し、各地で深刻な干ばつや山火事が発生。一方、巨大ハリケーンや豪雨被害も頻発。世界が異常気象に見舞われ続けた年となり、いよいよその深刻さが顕在化してきました。このような異常気象は企業にとって、施設へのダメージやサプライチェーンの寸断、従業員の健康被害など、企業の経営に多大な損害を及ぼす可能性があり、気候変動における対策をより加速させる必要性があります。
このような気候変動による自然災害の多発、米中対立やロシアによるウクライナ侵攻などの地政学リスクの高まりや新型コロナウイルス感染症によるパンデミックなどにより、BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)の重要性は増しています。気候変動による自然災害の頻発は「環境リスクへの対応」であり、「サプライチェーン・リスク」や「労働災害リスク」につながる可能性もあることから、「事業継続リスク」にもなるのです。
従来は考えもしなかったパンデミックが起き、紛争ではなく戦争が現実的に勃発する。企業活動を根本から揺るがしかねないリスクが発生している。こうした状況を受け企業経営者は、自社の事業が10年後も存続できているかという「存続リスク」を真剣に考え始めていると言われています。
BCPの目的は、事業を守り継続させることです。緊急事態時の適切な行動や体制を構築するなど、事前にBCPを策定しておくことで事業の縮小や倒産のリスクを軽減することにつながります。また、復旧を優先すべき事業が明確になることで、経営戦略の立案や見直しにつながり、企業の信頼性の向上にもつながるなどBCPの策定は有効とされています。
民間の信用調査会社(帝国データバンク)が約2万8千社を対象に調査したところによると、BCPを策定している企業はわずか18.4%で、内訳は大企業35.5%、中小企業15.3%となっています。想定することすら難しい事態を予想して対策を計画・準備しておくことは一見ハードルが高く見えますが、当協会は手順を追ってわかりやすくBCP作成のお手伝いをさせていただきます。危機管理のノウハウに長けた自衛隊OBが揃っていますので…
このヒイラギ通信が、皆様と当協会の橋渡しとして、今年も大いに役割を果たすことを心から念じています。
2024年1月10日
一般社団法人 防災訓練士協会
代表理事 安村勇徳