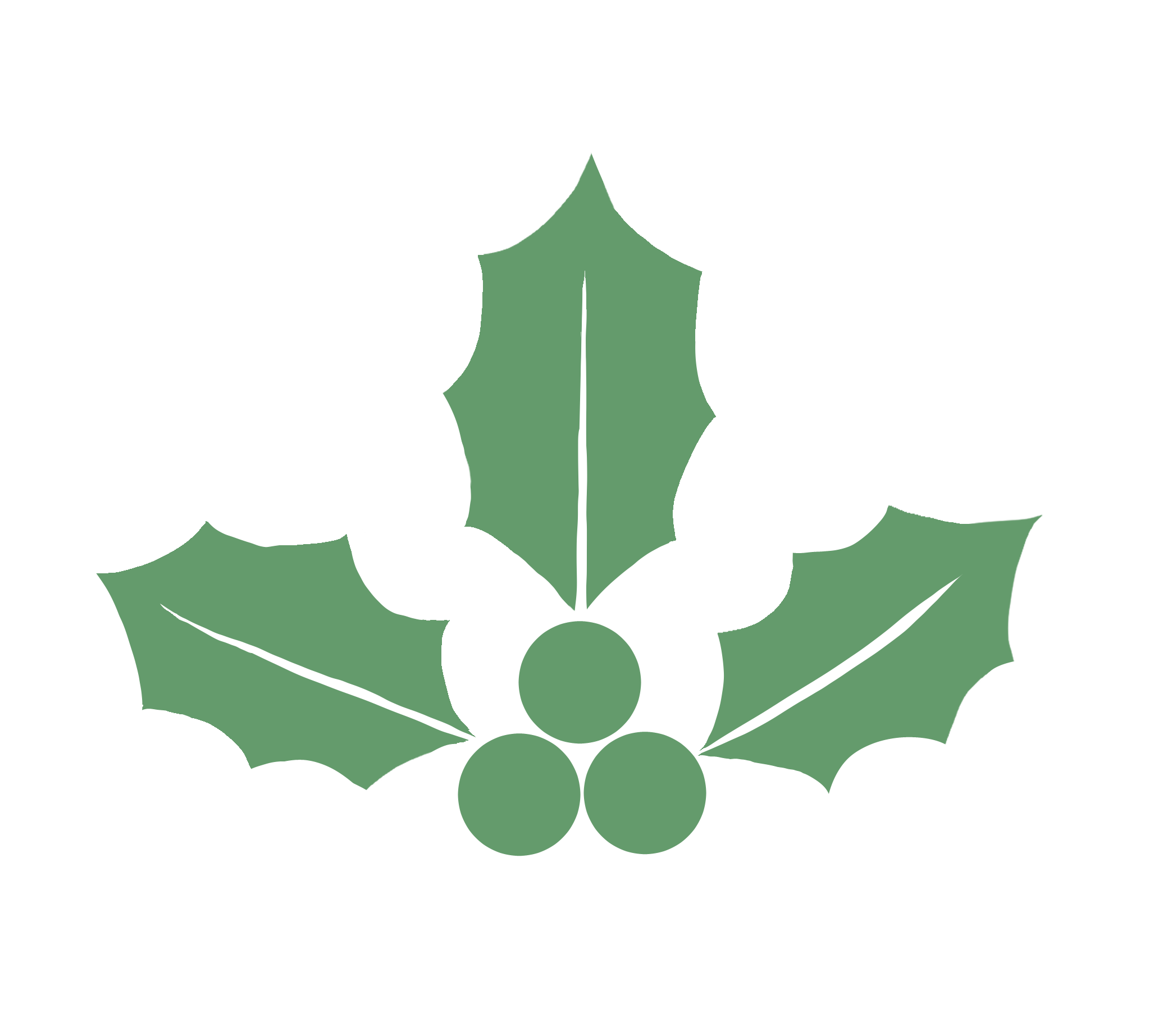能登半島地震発生から2カ月が経過し、明らかになった被害は、死者241名(災害関連死15名を含む)重軽傷者はあわせて1188人、倒壊家屋(全壊、半壊、一部損壊)は7万6824棟、石川県内の避難所では、あわせて1万1048人が依然として避難生活を余儀なくされている。さらにホテルや旅館など「2次避難所」に避難している人は合わせて4642人に上る。地震の発生直後県内約11万戸で断水、徐々に復旧作業が進んでいるが、依然として能登地方を中心に約1万8380戸で断水が続いており、石川県は一日も早い復旧を目指すとしている。北陸電力管内では、最大約4万戸で停電が発生し、新潟県内では約1,500戸の停電が発生した。1月下旬に早期復旧が困難な一部地域の約2,500戸を除いておおむね復旧したと発表された。
一方地元産業への被害も甚大である。伝統産業の輪島塗は、朝市通りの火災でこの地域に所在する12業者の仕事場が焼失したほか、ほぼすべての工房・事務所が全壊・半壊など甚大な被害を受けた。七尾市の和倉温泉は、建物などに大きな被害を受け、全旅館が休業、奥能登2市2町に所在する酒蔵は建物の全半壊や一部損壊の被害を受け、全11社で当該期の酒造りを断念する事態となっている。漁業への影響も深刻で、石川県内の60漁港に被害が出ており、漁港の共同利用施設26箇所が被害を受けている。広い範囲で地盤が数メートル隆起し外浦海域の21の漁港で海底が露出したり水深が不足したりしている。輪島市の黒島漁港では、地盤の隆起に伴い漁港内が陸地となり漁船の出航ができない状態となった。
能登半島に多く存在している電子部品や繊維の工場も大きな被害を受けた。能登半島に工場を持つ主要な企業26社のうち10社で従業員が被災したり、工場が被害を受けたりして、停電の影響もあり生産再開の目途が立っていない。一部の工場では一時操業を停止したがその後操業を再開、或いはまた、地震に伴い業績の予測が困難になったなどとして2023年度分の業績予想を取り下げている会社もある。
このように甚大な人的、物的被害をもたらしている今回の地震が、事業活動に与える影響について企業自身がどのように受け止めているのか?
東京商工リサーチ(TSR)が実施した、能登半島地震「事業への影響アンケート」調査の結果を紹介する。本調査は、2024年2月1日~8日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答4,872社を集計・分析したものである。
地震の事業へのマイナスの影響ついては、「あまり影響はない」が49.5%とほぼ半数を占め、「全く影響はない」が28.4%で、「影響なし」は約8割(構成比78.0%)に達した。一方、「少し影響がある」は18.8%、「大いに影響がある」は3.0%で、「活動に影響あるとする企業」は合計21.9%で、5社に1社が何らかの影響を受けていることになる。
企業の規模別では、「あまり影響はない」は大企業50.7%、中小企業49.4%、「全く影響はない」大企業22.5%、中小企業29.1%であり、これらを合わせると「影響なし」は大企業が73.2%、中小企業が78.5%と、ともに7割を超える。一方、「少し影響がある」は大企業22.3%、中小企業18.5%、「大いに影響がある」は大企業4.3%、中小企業2.9%であり、「活動に影響あり」は大企業で26.7%、中小企業は21.4%と、大企業が5.3ポイント上回っている。これは物流や取引先の被災など、地震によるサプライチェーンの問題があることから、広域で事業を展開する大企業への影響が大きくなっているとみられる。
どんな影響があるかを複数回答で得た結果は、「仕入(調達)に影響が生じている」が38.7%で最も多く、次いで、「販売(サービス提供)に影響が生じている」が32.8%、「取引先の拠点が被災した」が32.0%だった。大企業(128社)では、「取引先の拠点が被災した」が43.7%で最も高い。次いで、「販売(サービス提供)に影響が生じている」の36.7%、「仕入(調達)に影響が生じている」の28.1%と続く。中小企業(941社)は、最高が「仕入(調達)に影響が生じている」の40.1%で、次いで、「販売(サービス提供)に影響が生じている」の32.3%、「取引先の拠点が被災した」30.4%と続く。
都道府県別の影響では、「影響あり」は、被災地の石川県の65.3%を筆頭に、富山県61.8%、福井県46.6%の北陸3県に続き新潟県が35.0%と、震源地周辺の県で「影響あり」と回答した企業の割合が高かった。事業設備や取引先、サプライチェーンなどの被害に加え、従業員家族の被災から事業全体への影響が広がったとみられる。このほか、30%台は山梨県の33.3%、三重県の32.5%。取引先の被災で、販売(サービス提供)に影響が生じた企業が多い。地区別では、北陸が59.8%で他地区に比べて圧倒的に「影響あり」と回答した企業が多かった。次いで、中部25.9%、近畿24.6%と隣接地域への影響を反映している。
業種別は、最高が「宿泊業」の40.9%。以下、旅行業や冠婚葬祭業を含む「その他の生活関連サービス業」が38.0%、「機械等修理業」が37.5%の順となった。震災地の北陸3県は国内有数の観光地であるが、地震で旅行者が減少し、ホテル・旅館ではキャンセルも相次いだ。また、電気やガス、水道などライフラインも寸断され、宿泊施設の被害も大きい。「その他の生活関連サービス業」は、旅行客の減少や冠婚葬祭への影響が大きい。また、施設も被災したことで、事業に影響があったとみられる。
以上のような地震による事業活動への影響を受け、企業は今後どのような対策を考えているのか?
能登半島地震の発生を機に、企業として改めて大切だと考えた防災対策についてのアンケート(帝国データーバンク)の結果では(複数回答上位3つまで)
- 「飲料水、非常食などの備蓄」(39.2%)
- 「社内連絡網の整備・確認」(38.3%)
- 「非常時の社内対応体制の整備・ルール化」(31.6%)
- 「非常時向けの備品の購入」(28.4%)
- 「事業継続計画(BCP)自体の策定・見直し」(20.6%)
- 「災害で出社困難な場合の対応ルール化」(16.5%)
- 「災害時行動マニュアルの整備」(15.1%)
- 「自家発電設備の導入」(14.3%)
- 「建物や設備の強度確認、耐震補強」(10.7%)
- 「防災・避難訓練の実施」(9.6%)
なお、今回の地震を機に何らかの企業防災対策の大切さを改めて実感した企業は94.9%にのぼった。また、「BCPの作成・見直し」を挙げた企業が20.6%と5社に1社があるが、「災害時の対応マニュアルの見直し、策定を早急にする必要性を感じさせられた。」や「自然災害が起こる前に、建物老朽化の確認のほか、災害の起きやすい地域では事前に対策を講じる必要があると考えている。」とのコメントがみられるなど、BCPに基づく事前準備の徹底への関心の高まりにも注目される。さらに、企業からは、「自然災害の強力な破壊力に対し、何かをするというより、起きた後の社員と社員の家族の生活をどのように安定させるかということを真剣に考えるきっかけになった。」や「危機管理の重要性を再認識した。緊急連絡網の整備と災害時での対応を常に議論することが重要だと実感した。」といった声が紹介されている。
能登半島地震が企業活動に与える影響とその対策について紹介しましたが、いざという時に備え対応策を計画し、これを実行できる体制の整備・確認と訓練の徹底が重要であることをご理解いただけると思います。当協会は、BCP策定から訓練マニュアルに基づく実践的訓練まで、災害に強い企業つくりをトータルでサポートさせていただきます。
2024年3月10日
一般社団法人 防災訓練士協会
代表理事 安村勇徳