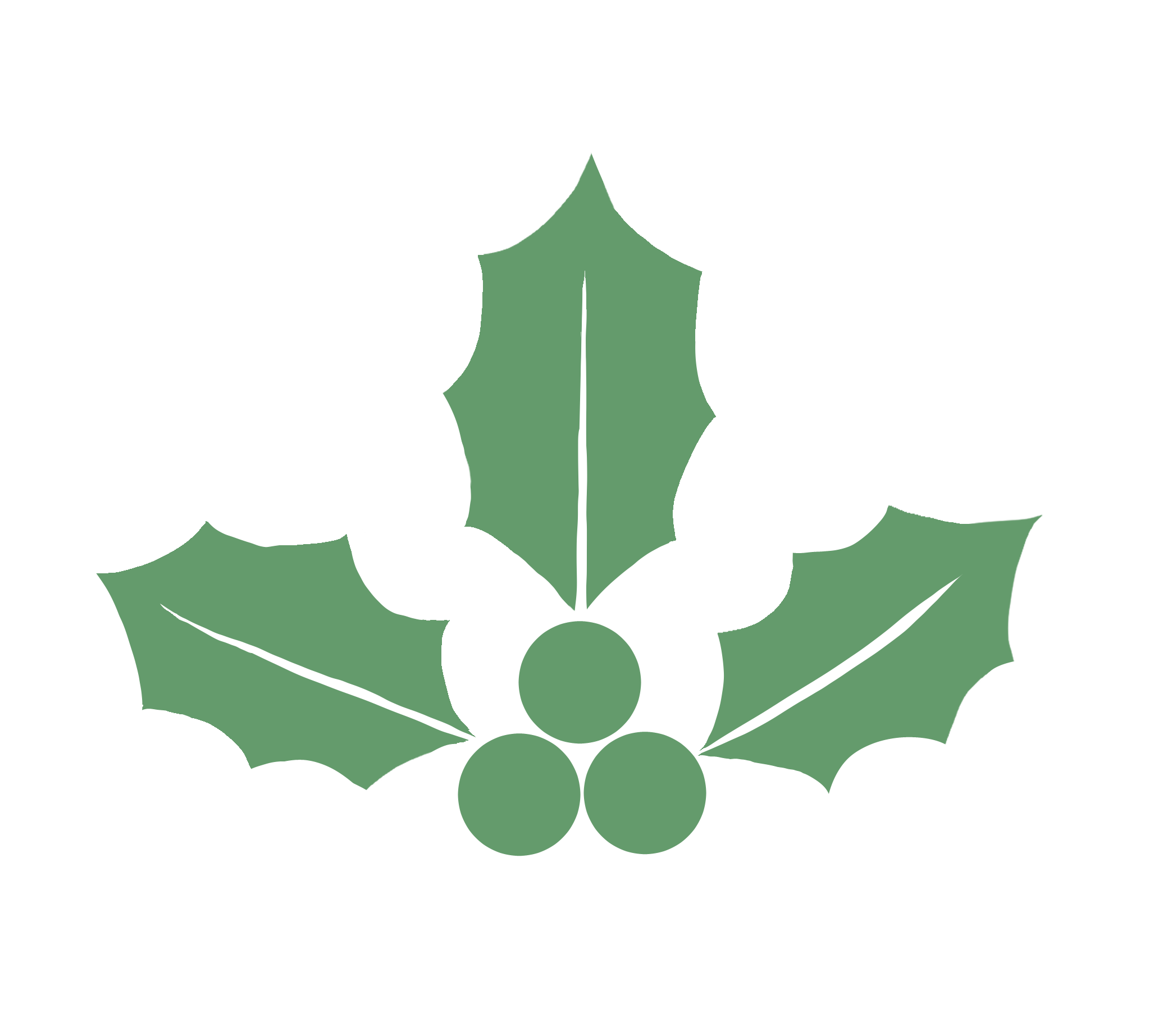2024年4月3日中華民国(台湾)の東方沖合で発生したマグニチュード7.2の巨大地震は、景勝地として知られる渓谷など人気の観光地である花蓮県を中心に大きな被害が発生した。1月1日の能登半島地震に引き続く巨大地震の発生は、大きな衝撃を持って報道され、改めて災害対策の重要性を認識させられるきっかけになったものと思われる。このような未曾有の大災害の発生は、誰もが被災者になる可能性があり、企業にとっても従業員や顧客の安全を守り事業存続を図るために、事前の防災対策が欠かせない。
BCP(事業継続計画)の策定はそのための第一歩であるが、計画に基づき備蓄品の準備や耐震対策といった事前の備えをしていても、イザという時にスムーズに行動できるようにしなければ、被害を防ぐことができない恐れがある。災害発生時の役割分担を定め防災訓練を定期的に行うことで、計画を周知徹底するとともに防災意識の啓蒙や、防災対策の理解を進める必要がある。
訓練の重要性は理解していてもイザとなればなかなか実施できないのが防災訓練である。筆者が東北方面総監部(仙台)に勤務していた時、東北6県の災害派遣の現地研究に岩手県の田老町を訪れた。当時は、明治、昭和の2度にわたる巨大津波の教訓から「万里の長城」と呼ばれる高さ10メートルの防潮堤を構築して、東北随一の津波対策を誇っていた。我々の訪問を受け、現地案内や過去の災害の経験談など町を挙げて歓迎されたが、視察途中に「自衛隊さんが来てくれて良かった。普段は防災訓練を計画してもほとんどが無関心なのに…」と耳元で囁いた市役所の防災担当者の本音が印象的であった。3.11の東日本大震災による津波はこの防潮堤を超え、「津波防災の町」を宣言した田老の町を飲み込み、甚大な被害を及ぼした。「防潮堤があるから大丈夫」「津波が越えるわけがない」。こう口にして避難をしなかった人もいたという。避難訓練を徹底することの重要性がここにある。
ヒイラギ通信2月10日号でご紹介した帝国データーバンクのアンケートによると、能登半島地震の発生を機に「何らかの企業防災対策の大切さを改めて実感した企業」は実に94.9%にのぼった。その防災対策について具体的な項目は、①「飲料水、非常食などの備蓄」(39.2%)、②「社内連絡網の整備・確認」(38.3%)、③「非常時の社内対応体制の整備・ルール化」(31.6%)、④「非常時向けの備品の購入」(28.4%)、⑤「事業継続計画(BCP)自体の策定・見直し」(20.6%)、⑥「災害で出社困難な場合の対応ルール化」(16.5%)、⑦「災害時行動マニュアルの整備」(15.1%)、⑧「自家発電設備の導入」(14.3%)、⑨「建物や設備の強度確認、耐震補強」(10.7%)、⑩「防災・避難訓練の実施」(9.6%)となっている。このような結果を見ると、防災対策のためにやるべきことがいかに多いかが明らかになるとともに、これらの施策の実効性を担保するための検証や事前訓練の必要性が痛感される。
企業が行う防災訓練は、生産ラインの維持や流通の確保、或いは営業活動に伴う顧客対応など、中断することのできない多様な業務を継続する中で実施せざるを得ない環境にある。この点、自衛隊が行う有事の任務を想定した訓練・演習は、それそのものが本来業務であり、企業が業務を中断して行う訓練とはその前提が大きく異なっている。しかしながら将来起きてほしくはないが、もしかして起こるかもしれない万一に備えるという観点からは、訓練のやり方について参考になることは少なくないと思われる。
自衛隊の訓練・演習は、「シナリオにもとづくロールプレー」ともいうべきものである。これは様々な有事のシナリオの中から、ある場面を切り出しそれぞれの役割を決めて、与えられた役割を繰り返して演ずることで、有事への対応に習熟させる方法である。シナリオの種類も多く、分担する役割も複雑多岐にわたることから、訓練の機会はいくらあっても足らないのが実情である。その中から優先すべき課題を選んだり、とりあえず出来るところからやってみたりと、試行錯誤することで参加者の意欲を高める工夫も出てくることとなる。
一般的な防災訓練の種類には、機能別・個別訓練として、①連絡・通報訓練;災害発生時の安否確認をスムーズに行うための訓練、②初期消火訓練:建物に備え付けられている消火設備の確認や使用方法の確認を行う訓練、③避難訓練;災害直後、迅速に安全な場所まで避難するための訓練、④応急救命訓練;心肺蘇生法やAEDの使い方、怪我人の搬送方法、三角巾の使い方など、応急救命の方法を学ぶ訓練、⑤救助訓練;閉じ込めや備品転倒により人が下敷きになった状態などを想定し、救助用品や身近な道具、工具、担架などを利用して負傷者を救出する訓練などがある。また総合訓練・演習としては、災害発生を想定して図上で被害想定や状況整理・対応方法などを演練する図上演習や現地・現物を利用して行う現地・実動訓練などがある。
防災対策として筆者が推奨するのは、「自然災害別の対策マニュアル」に基づく訓練である。「自然災害」といっても「大地震」「津波」「活火山の噴火」「台風」などさまざまで、どれも同じ対策で十分とは言えない。さらに具体的な自然災害の被害は、海や川沿いであれば「津波」「洪水」のリスクが大きく、山沿いであれば「噴火」「土砂崩れ」「雪崩」のリスクが大きいなど、地域によって災害の様相は大きく異なる。このことから、営業所や支店のある地域の特性に応じた対策マニュアルが必要となる。
当協会では、それぞれの企業の支店・営業所が所在する地域の特性に応じたBCPの作成を提案しているところですが、この度新たに、それぞれの特性に応じた訓練マニュアルを作成し、BCPに元づく訓練をお手伝い出来るよう準備中です。経験豊富な自衛隊OBの会員が、個別・機能別訓練はもとより、シナリオに基づく図上演習・総合訓練をサポートさせていただきます。このような訓練を通して、防災対策の見直しやBCPの見直し・修正、さらには災害時にとるべき行動を周知するとともに防災意識を高めることができるものと信じています。いつでもお気軽にお問合せください。お待ちしています。
2024年5月10日
一般社団法人 防災訓練士協会
代表理事 安村勇徳