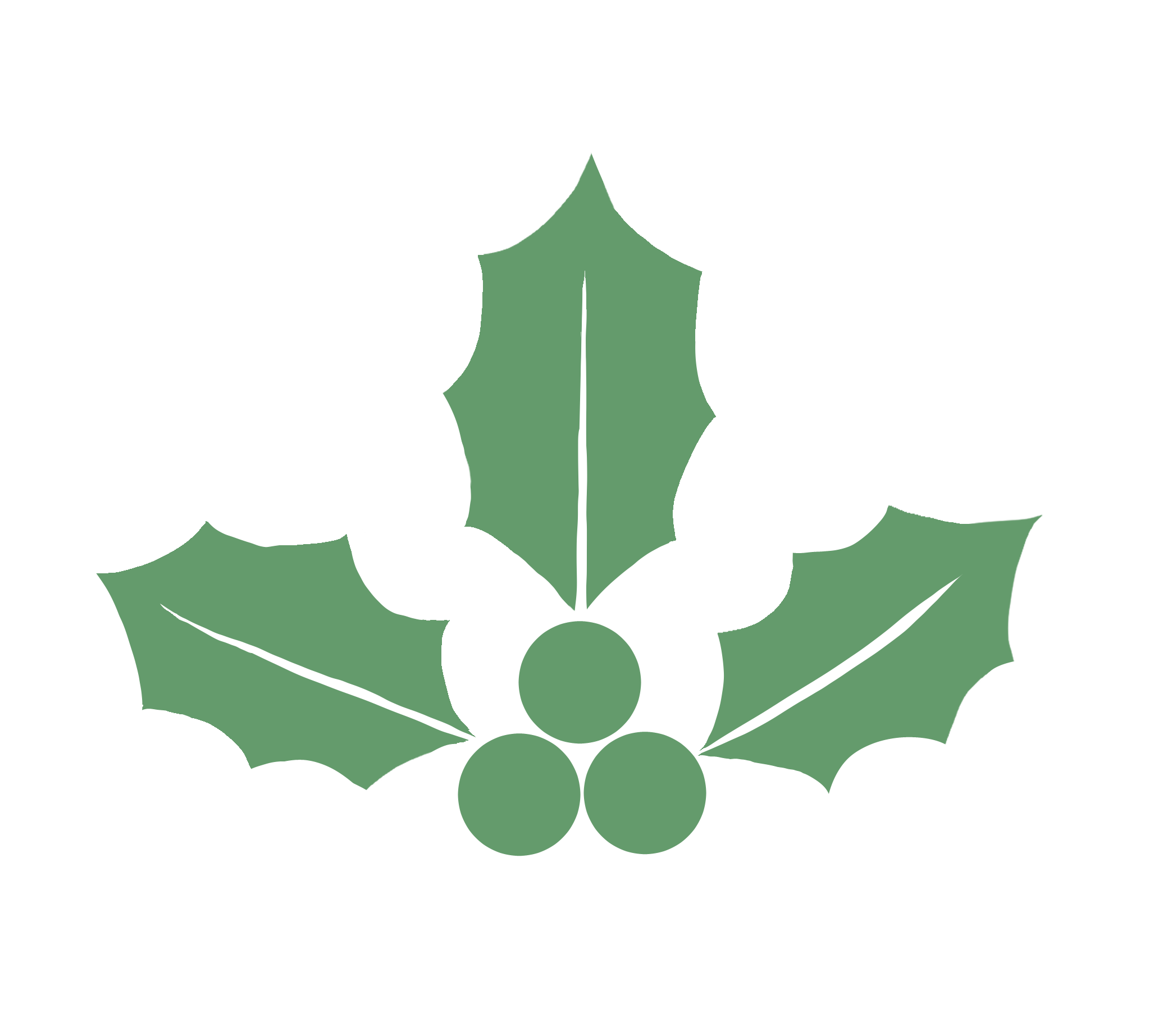はじめに
昨年、「情報活動の実施について」の記事を投稿させていただきましたが、ここ最近災害に限らず、国際紛争や経済動向などで偽情報が飛び回り、どれが正しく、どれが正しくないのか、判断が困難で、思考や行動に支障を及ぼす場面が多々発生しています。
特に災害発生直後においては、いろいろな情報が飛び交い、必要な情報は入手出来ないなど、安全や業務遂行に影響を及ぼしています。
このような中で、被害を最小限に抑えるために災害関連の正しい情報、時機に適する情報について述べさせていただきます。
1.正しい情報を把握するために
(1)正しくない情報(偽情報)の変遷
1923年に発生した関東大震災においては、流言として、一部の人達による偽の犯罪や暴動の発生が伝えられ、一方、火災や倒壊家屋などの被害状況は上手く伝わりませんでした。
1995年に発生した阪神淡路大震災においては、極一部の地域で暴動の発生が伝
えられましたが、偽情報として拡散するには至りませんでした。小さなデマは多くありました。
2011年に発生した東日本大震災においては、インターネットを利用した偽ツイートが多く出現しました。
2024年1月に発生した能登半島地震においては、SNSに偽の救助要請や被害状況などのデマが多く寄せられました。また、最近では各所でAI生成を使用したデマやフェイク動画などが発生しています。
(2)情報源の信頼性と経緯からの妥当性
デマやフェイク動画などは、愉快犯や国、自治体、企業などの混乱や信頼の失墜を意図する勢力、個人によると考えられ、企業においては業務の混乱や経営に対する信頼失墜につながり兼ねません。
そのため、情報の収集に当たっては、まず複数の情報源を持ち、各情報源については信頼性の度合いにより、ランク付けします。
例えばABCランクに区分し、国の機関や自治体、マスコミのニュース部門、当該社員はAランク、マスコミのその他部門、協力会社、近傍の会社、住民はBランク、SNSなどインターネットを媒体としたものはCランクと設定します。
次に情報源から得た情報を、経緯からの妥当性の度合いによりランク付けします。
例えばABCランクに区分し、正しい情報の可能性としてAランクは極めて高い、Bランクは高い、Cランクは低い、と設定します。
経緯からの妥当性を評価するためには、それまでの災害や国、自治体、近傍住民等の対応状況などを継続的に記録把握し、その流れに沿って逸脱していないかどうかで、あり得る状況か見ていきます。
この際、災害時の計数的尺度を出来るだけ持つようにします。例えば、氾濫した河川水は10分程度で床上まで浸水する、町の中心部まで普段車で15分位だが大混雑時には2時間位かかる、ハザードマップに載っている数値などです。
この尺度も上記のあり得る状況かを観るバロメーターになります。
経緯からの妥当性がB以上であれば情報として使用することになるでしょう。
情報源の信頼性と経緯からの妥当性共にCランクであっても、事実の可能性が少しでもあれば記録しておき、否定情報として確認することが望ましいです。
2.適時な情報を把握するために
災害発生直後、情報は錯そうし、欲しい情報はなかなか入手出来ないということが考えられます。
特に、大規模地震や台風、集中豪雨による大規模風水害、火山噴火は発生の位置や規模は収集できるものの人命や倒壊家屋、道路や河川などの被害は国、自治体、マスコミを通して逐次に拡大します。
そのため、限られた情報から最悪の状況の推移を予想し、必要とする情報を先行的に見積り、逐次入手した情報は、入手した時間及び情報内容の発生した時間を記録し、時系列的に整理しながら活用します。
2024年2月10日
一般社団法人 防災訓練士協会
理事 吉元慶司