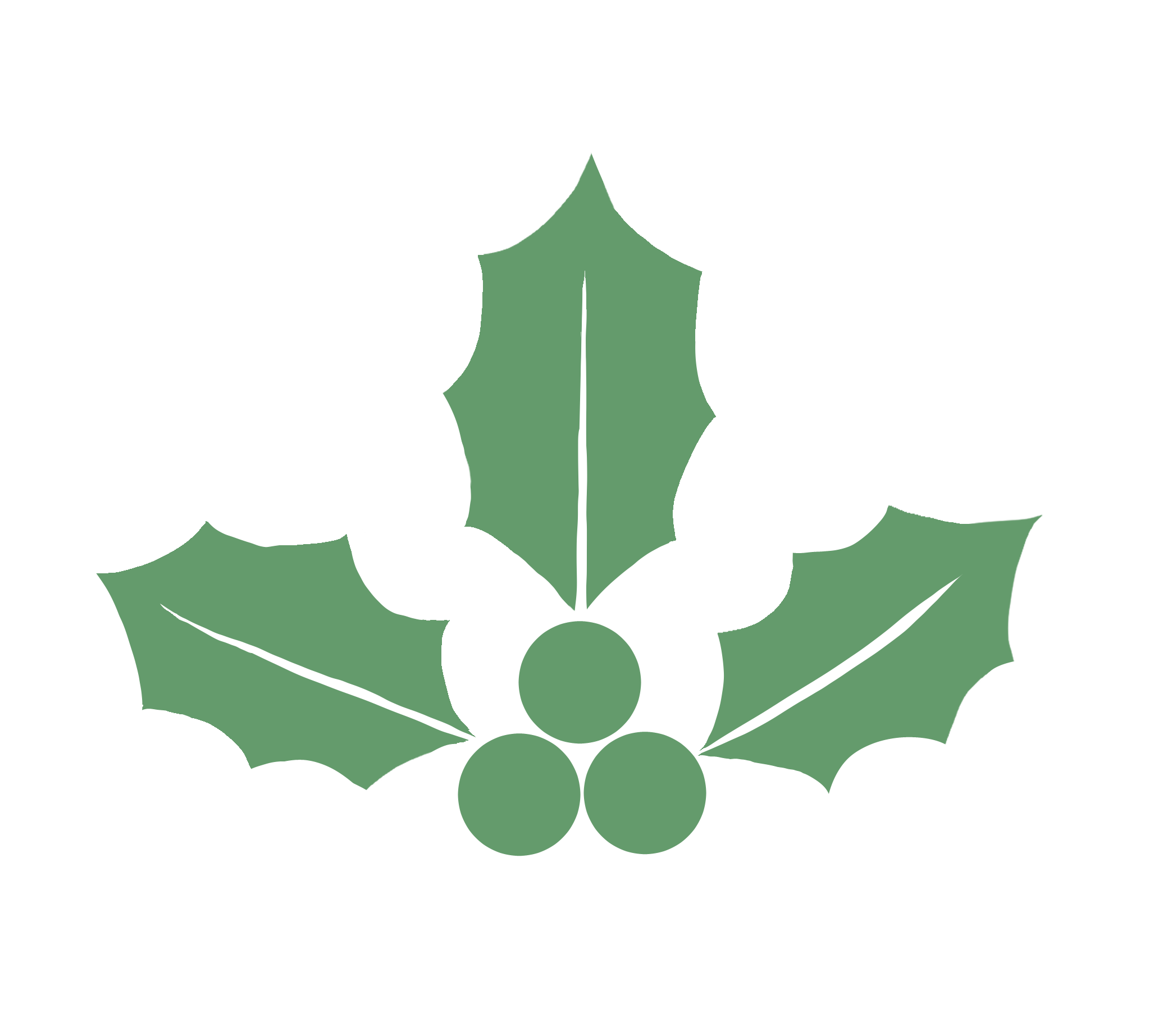前号に引き続き、防災訓練について参考になると思われることを、書いてみようと思います。防災訓練の種類には、機能別訓練と総合訓練があることを紹介しましたが、訓練の段階で区分すると、基本的なことを繰り返し行う基礎訓練と、さらなるレベルアップを求めて行う応用訓練があります。さらに訓練の規模で区分すると、小グループで行う目的を限定した小規模訓練と複数のグループを集めて行う訓練がある。訓練は小規模な訓練から少しずつ規模大きくしたり、小規模なグループを対象にした基礎的な訓練を機能別に行い、次いで応用訓練、或いは総合訓練へとレベルアップをしたりするのがお勧めの訓練要領の一つである。
北海道の東半分(道東)の防衛警備を担任する第5師団(当時)の師団長を務めていた筆者が退官の直前に当面した課題が「2000年問題」である。当時のコンピュータが20世紀から21世紀へ移行するときにどんな問題が生ずるのかは全く未知の経験であった。様々な憶測や議論が交わされる中、自衛隊として「何かに備える必要があるのか?」そのために「今なにをするべきか?」。上級司令部からの指示の有無にかかわらず、師団で出来ることは準備しておこうということで考えたのが「通信訓練」である。どんな事態が生起しても、必要な相手と、必要な時期に必要な通話・通信ができるよう備えておくことが、今求められていると考えたのである。
このため師団が持っているすべての通信手段を総ざらいして、機材を点検・整備し、固定局・移動局を問わず実際に開設運営し、相手との通話・通信を確認することとした。順調だった訓練の最中、思いがけない問題が報告された。「使えない防災無線機がある」とのこと。調べてみればこの無線機は、1995年(平成7年)の阪神淡路大震災の教訓から自衛隊と自治体との連絡を確保するため、急遽調達し全国の陸上自衛隊の部隊に配布されたものであった。このため阪神地区の自治体との通話はできるが、地元の自治体の無線機とは周波数帯が異なり通話できないというわけである。使えない無線機が5年間一度も使われることもなく災害派遣用として“大切に保管”されていたことになる。
早速この無線機の活用方法について検討を命じた結果、無線機の端末を自治体に貸し出すことで相互の通話を確保することに活用することとし自治体に提案、訓練にも取り入れることにした。このように思い付きで始めた通信訓練の成果が思いがけないところに得られることとなったのである。このような緊急時の連絡通信手段を確認し訓練しておくことは、企業の防災対策としても有用である。災害時に利用可能なすべての通信手段を改めて確認し関係者の間で認識を共有しておくことで、安否確認の手段を確保し、社員に対する出社の要否・在宅勤務の要領などの指示や顧客との緊急連絡手段の確保などに活用するなど、通信訓練の効用は枚挙にいとまがない。特に被災直後の安否確認のために、その時点でどのような通信手段が利用できるかは重要で、公的な通信手段をはじめプライベートなスマホの利用も含め、いざという時のルール作りが必要であろう。
このような機能別・基本的な訓練として一度はやっておきたいのが、災害用資器材・備蓄品の点検、配分計画や使用方法の確認などを行う訓練である。この訓練は、普段開ける機会の少ない防災備蓄倉庫を棚卸的に開放して在庫を確認し、配分計画に基づく備蓄品配分の手順や、簡易トイレや発電機・照明具、テントなど災害用の装備品の使用方法を確認・演練する格好の機会となる。トイレやテントの組み立てなど一度でも経験があれば大きな問題なくできるが、まったく初めてであれば、どこから始めていいのかでさえ判断しかねることも少なからずあるものである。筆者が防災指導員として町内会の防災訓練に参加した時のこと、町内会長から「その指導」を突然依頼された。自分で組み立てることすらおぼつかないのに、これを指導するなんて…。
そこで一計を案じた。「皆さんは、災害が発生しとりあえず広場に集まった。」「防災倉庫のカギは空いているが、指導できる人が見当たらない。」どうすればいいのか?
などと、問いかけ。とりあえず何があるか倉庫の中を確認しましょう。その前に、グループ分けをして、リーダーを決めるといいですよね。このようなアイディアを出し合うことでなんとなく作業の手順が整い始める。取り扱い説明書があったと歓声が上がったり、部品が足らないとか余ったりとか、かなり盛り上がりながら作業は進み、それぞれグループごとに無事完成を迎えることとなった。最初から適任の指導者が得られなくても、工夫次第で訓練の成果は上げることができる事例である。
本来、防災訓練は計画をしっかり作成し、できればリハーサルをして、初心者が安心して参加できる土俵を整備し、防災訓練士のような専門知識を習得したベテランの指導者が模範を示しながら、段階的に練度向上を目指すのが、理想的な訓練ではあろう。防災センターなどはそのような訓練を提供する場として利用することもできるが、それぞれの企業が抱える防災に関する環境は多様であり、ニーズに合った訓練の場を求めることは容易ではない。本稿でご紹介したように、ちょっとした工夫で気軽に始めた訓練で思いがけない成果を収めることは少なくない。訓練計画の作成に長時間頭を痛めることなく、思い切って訓練をやってみることである。当協会は、多忙な企業の担当者をお手伝いし、支店・営業所の置かれた防災上の特性を分析した訓練メニューを提供できるよう準備を進めています。お気軽にご相談ください。
2024年6月10日
一般社団法人 防災訓練士協会
代表理事 安村勇徳